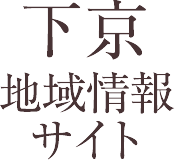小さいながらも存在感を放つ神社
JR丹波口駅周辺を歩いていると、小さな神社を発見しました。神社の名前は島原住吉神社。普通に歩いていれば気づかないほどの場所にひっそりとたたずんでいますが、こういう小さな神社でもしっかりとした歴史を有しているのではないか。過去に思いを馳せることが好きな私はそう思い、気になったのでこの神社について調べてみました。

島原住吉神社は、もともとこの地に住む住吉屋太兵衛という人の自宅で祀っていた商売繁盛の神様である住吉大明神を起源とします。この神様が良縁のご利益があるということで大変人気となり、参拝者が多かったため、改めて自宅の外に祀るために1732年に神社として建立されました。当時はその規模はとても大きく、南は道筋(島原中央東西道)から北端に及ぶほどの境内地を有していたそうです。そして、かつて花街であったこの地で、太夫や芸妓が仮装して行列をつくり練り歩く「練りもの」が行われていました。祇園のそれに比べれば規模はそれほど大きくはないものの、それでも盛大な行事だったようです。
ところがこの神社は私社であったため、明治維新後、国が神社を統括するようになると廃社となってしまいます。しかしながら、地元住民の篤い信仰心があったため、1903年には付近にあった稲荷社を引き継ぐ形で再興しました。その時に現在の狭い境内地となり、また社名として住吉神社は認められず、稲荷神社とされました。その後2001年に社名が現在の島原住吉神社となりました。

島原住吉神社の境内には、幸(さいわい)天満宮という社もあります。こちらは揚屋町の会所にあった天神(菅原道真を祀った神社)の祠が1734年に移ってきたものだそうです。ここでは、福岡の太宰府天満宮に倣い、鷽替え(うそかえ)の神事が営まれていました。鷽替えとは、前年の災厄を噓とし、本年が吉となることを祈願する行事で、本来は鷽という鳥の木像を「替えましょ、替えましょ」という掛け声とともに交換し合うものです。この幸天満宮では鷽の木像ではなく、代わりに色紙や短冊を交換し合っていたとのことです。この行事はかつて甚だしく行われていましたが、現在では廃れてしまったようです。

また島原住吉神社の北には大銀杏の木が植えられています。これは明治維新後に島原住吉神社が廃社となった後も神木として遺されたものです。1930年にこの木の根元に弁財天が祀られることにより、
さらに神木として崇められるようになり、今では樹齢300年相応の島原一の巨木となっています。
島原住吉神社は一見すると小さな神社ですが、この神社に初めて訪れたとき、私は存在感のある神社だと思いました。古いながらも鳥居がどっしりと構えており、中には社が二つあり、また歴史を記した石碑が建てられていたからです。そして地元住民の篤い信仰心があったために再興したという歴史を知ったことで、私はこの神社からそういった地元住民の熱い思いや、かつては大規模な神社であったという歴史の重みを感じます。私は神社などを訪れ、過去の人々の思いを想像して追体験することが好きなのですが、この神社を訪れると、かつて行われていたであろう華やかな祭事の光景や、多くの人々が熱心に信仰してお参りに訪れていた光景が思い浮かびます。そして現在ではそういった祭事なども行われることがなくなり、規模も小さくなった様子もまた、趣があると思います。また、この島原の地は神様への崇拝心の強い素敵なまちであると感じました。
(下京ローカルグッドレポーター:Kotaro)
2023.10.20