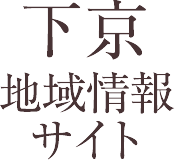歩いて体感!住宅街の中の歴史地区
京都の歴史地区といえば、東山の産寧坂や嵯峨野地区などが人気で多くの人が訪れています。下京区は京都駅があり、京都の玄関口としてのイメージが強いかと思いますが、実は下京区の中にも古くの街並みが残る地区があります。
丹波口駅から徒歩5分ほど、現代風の住宅街の一角で一際「京都らしさ」を放っている地区が花街として栄えていた島原地区です。島原は寛永18年(1641)に設けられた我が国最初の公許花街です。
東から向かうとまず見えてくるのが島原大門!!住宅街の中で一際目を引くその門を見れば、気分は一気に冒険気分に!黒の壁と瓦で作られていて、両脇の提灯が良いアクセントになっています。現在の門は一度焼失した後、慶応3年(1867)に立て直されたもののようです。

写真は外側から見たものですが、内側から見るとまた変わった形の門に見える…かも…?

門から一歩中に入ると街の雰囲気が変わります。
アスファルトではなく石畳で舗装された街路がこのような京都らしさを感じる理由でしょうか。少しの変化だけで「日本らしさ」を感じてしまうのは不思議ですよね。
島原でまず行ってほしいのが角屋もてなしの文化美術館です。
角屋はもともと揚屋(現在でいう料亭)で、江戸時代には新撰組の隊士たちが宴会をしていました。現在は美術館としての企画展示のほか、新撰組についての展示もされています。中には新撰組がつけたとされる刀傷があるようで、当時の活気の面影が窺えます。開館期間が限定されているので訪れる際は事前に要チェック!(私は入れませんでした…泣)

運悪く入れなかったとしても大丈夫!島原は歩いているだけで面白いまちで、他にも魅力はいっぱいあります!例えば角屋の外壁に注目してみると、場所によって色や材質が違っていることに気づきます。私は増築や改修が何度も行われてきたからかなと思っているのですが、実際のところはどうなのでしょうか。このように過去に思いをはせながら歩くこともまちあるきの醍醐味ですよね。

続いては輪違屋です。
こちらは元禄年間(1688~1704)に創業したとされる置屋で島原に現存する唯一の置屋として現在も営業を続けています。一般公開はされていませんが、2023年7月8日(土)から8月31日(木)、9月16日(土)から24日(日)のみ、特別公開されていて普段は入ることのできない一般の方も入ることができます。私も期間内に再訪して中の様子を体感したいな~なんて思っています。

島原地区にはこのような歴史的建造物以外にも銭湯や旅館、カフェ、一般の方の住居などがあり、生活の中での京都を感じられる面白い地域です。私自身、京都に引っ越してきて3年目にして初めて訪れたのですが、その雰囲気に魅了されました!!
この機会に是非島原に足を運んでみてはいかがでしょうか。


(下京ローカルグッドレポーター:Nao)
〇参考文献
京都市, 2022, 「京都市指定・登録文化財-建造物(下京区)」, 京都市情報館 (2023/07/27取得, https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000189689.html)
2023.10.11