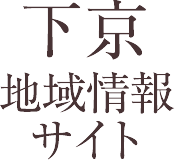とう ろう どう燈籠堂
今年の祇園祭での山鉾巡行はコロナウイルスの影響で中止となりました。神事として榊を捧げて斎行されましたが、このような形式での斎行は、昔応仁の乱で中止となった折に室町幕府からの指示でされたことがあり、今回はこれに倣ったものであるとか。室町幕府は今も健在のようです。
さて、東洞院通松原上ルに保昌山を護持する燈籠町があります。平安時代末期、東山小松谷に三十三間堂に匹敵する四十八間(1辺が十二間四方)の精舎がありました。各柱ごとに1体づつ全部で48体の阿弥陀如来を安置し、48の燈籠を揚げ女房たちに昼夜灯が絶えないように世話をさせ、その輝くさまはあたかも極楽浄土の世界であったようです。
そして毎月14、15日には、融通念仏会を行い、念仏を唱え終わると女房たちが鐘や太鼓をたたいて「心のやみの深きをば 燈籠の灯こそ照らすなれ 弥陀の誓いをたのむ身は 照らさぬところはなかりけり」と謡いながら堂内を回「礼賛行道」を行ったとあります。このようなところから燈籠堂と呼ばれました。平家の滅亡によって精舎は寂れてしまいますが、室町時代に立誉上人によって東洞院松原において、浄土宗のお寺として再興され、後花園天皇より「浄教寺」の勅額を賜りました。その後、豊臣秀吉の京都改造により寺町通四条下ルの現在の場所に移転しました。保昌山のある町内の名前の由来はこの燈籠堂から来ています。
さて問題です。
この燈籠堂を造営し、「燈籠大臣」と呼ばれた平家の公達は誰でしょうか。
① 平 清盛
② 平 重盛
③ 平 維盛

浄教寺境内
正解
② 平 重盛
この問題は,京都検定1級をお持ちで、区にゆかりのある方に出題していただいています。
※市民しんぶん下京区版「下京のひびき」令和2年9月15日号掲載時の内容です。
2020.09.15